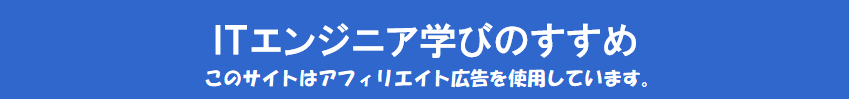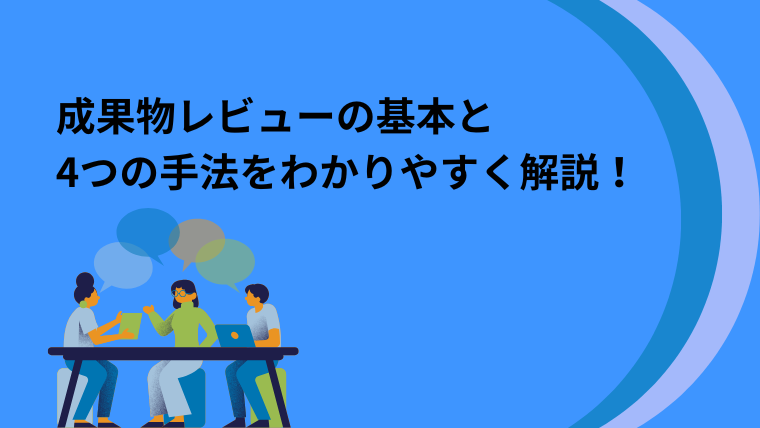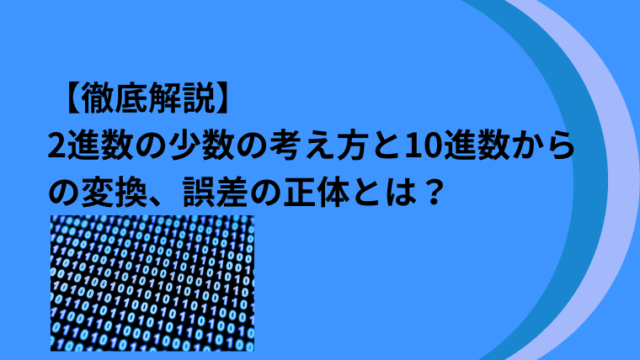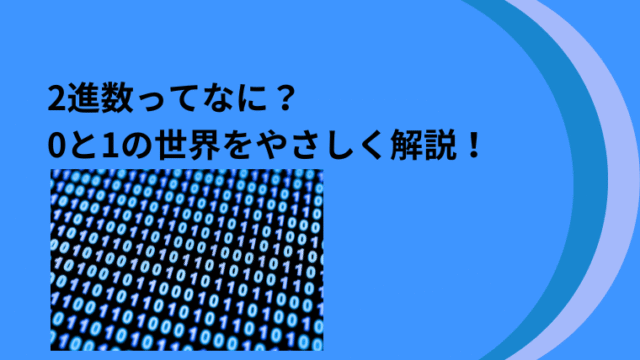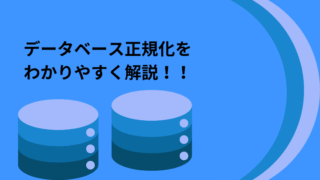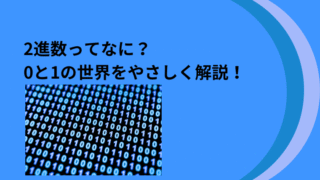1. なぜレビューが必要なのか?
開発や執筆の現場では、人間である以上ミスは避けられません。
コードのバグ、要件漏れ、誤字脱字、曖昧な表現、表現のゆらぎなど、さまざまな「見落とし」や「思い込み」「勘違い」が起こり得ます。
レビューを行い他人の視点を入れることで、成果物の品質向上やリスクや課題の早期発見、またチームメンバー間の知識や方針の共有といった効果を得ることができます。
特にソフトウェア開発においては、レビューにより検出される不具合を修正するコストは工程が後ろになればなるほど跳ね上がっていきます。
リリース後にバグが発見されると修正コストが跳ね上がるため、早期のレビューが非常に重要なのです。
ソフトウェア開発やドキュメント作成の現場で欠かせないのが「レビュー」です。
この記事では、レビューの重要性を理解しから代表的な4つのレビュー手法(ウォークスルー、インスペクション、ラウンドロビン、パスアラウンド)まで、わかりやすく解説します。
情報処理試験でも出題される内容ですのでそれぞれのレビュー手法の目的やレビューの実施方法を理解し、試験対策や実務に活かしていきましょう。
2. ウォークスルーとは?
ウォークスルーは、レビュー対象の成果物の作成者が主導して、関係者に内容を説明しながら意見や指摘をもらう形式のレビューです。
設計上の問題点を早期に発見することを目的として、工程の終了時点や成果物の作成時点で実施します。
レビュアーは成果物のソースコードや設計書から記述されたシステムやソフトウェアの動作を机上でシミュレートして問題点を発見します。
・原則として管理者には参加させない
・誤りを見つけることを主目的として、解決策までは議論しない
・事前に資料を配布しておくことで短時間で効率よく行う
といった特徴があります。
3. インスペクションとは?
インスペクションは、形式的で厳格なレビュー手法です。事前に参加者へ成果物を配布し、ルールに基づいて不具合を洗い出すことに特化しています。
成果物作成者以外の参加者がモデレーターとして主導すること、公式な記録、分析を行うことが特徴です。
例えば、成果物それぞれに対してウォークスルー、パスアラウンドによるレビューが実施されていることをルールとしているのであれば、その記録が残っているか?を確認します。
また成果物に対するレビューの指摘の数や指摘に対する重要度を指標として分析し、システム全体の品質の傾向を客観的に見ることができます。
4. ラウンドロビンとは?
ラウンドロビンは、参加者が順番に内容を読み上げ、確認しながら進めるレビュー手法です。
読み上げることで成果物への内容への集中度が高まり、見落としを防ぎやすくなります。
また参加者全員の参画意識も高まります。
一つ一つを読み上げていくので時間がかかってしまいますが、その分認識や方向性のすり合わせの精度は高まります。
5. パスアラウンドとは?
パスアラウンドは、成果物をレビュー担当者に順番に回して確認してもらう手法です。
ミーティングを必要としないため、時間と場所の制約が少ないのが魅力です。
メールによる添付での送付、成果物を共有フォルダに配置などによりレビュアーに対して案内を周知します。
時間と場所を制約しない分、レビュアーにいつレビューを実施してもらえるからレビュアーにゆだねられてしまうので、期限を切って対応してもらう必要があります。
6. まとめ
以上がレビュー手法の説明でした。
簡単にまとめますと下記のとおりです。
<ウォークスルー>
成果物の作成者が説明、非公式、机上シミュレートしながらレビューをする
<インスペクション>
責任者がモデレータとなり説明、形式的なレビュー、事前準備必須
<ラウンドロビン>
参加者が持ち回りで読み合わせ、参画意識が高まる
<パスアラウンド>
成果物をメールなどで回覧、時間や場所に制約されない
レビューにはそれぞれ目的と適した手法があります。
重要なのは、チームやプロジェクトの状況に応じて適切なレビュー手法を選択することです。ぜひ、この記事を参考に、より効果的なレビュー文化を築いていきましょう!